
寺院や神社にある玉ねぎの形

寺院や神社でみかける玉ねぎの形
これらは擬宝珠(ぎぼうしゅ又はぎぼし)と呼ばれています。

擬宝珠(ぎぼうしゅ)の由来は主に2つあるそうで、
1つは、仏教における宝珠(ほうじゅ)を擬しているという説、
1つはネギの花を模して作ったという説です。

宝珠(ほうじゅ)は、
宝物を出す
病気を治す
毒蛇を消す
にごり水を浄化する
災いを防ぐ など、あらゆる願いを叶えると言われる不思議な珠(たま)といわれています。

仏教の言葉で、願いごとがすべて聞き入れられるというふしぎな宝の珠(たま)の意味で、
民衆の願いを成就してくれる仏の徳の象徴であります。

お地蔵様も宝珠を持っております。

では、もう1つの説、なぜネギの花を模して作ったのでしょうか?

ネギの独特の臭いが魔よけになると信じられていて、その力にあやかるために使われるようになったようです。

また、擬宝珠(ぎぼうしゅ)は装飾としてだけでなく、頂部を腐食から守る役割ももっています。

玉ねぎの形をした擬宝珠(ぎぼうしゅ)
なんだか癒やされませんか?
是非、身近にある擬宝珠(ぎぼうしゅ)探してみてください!


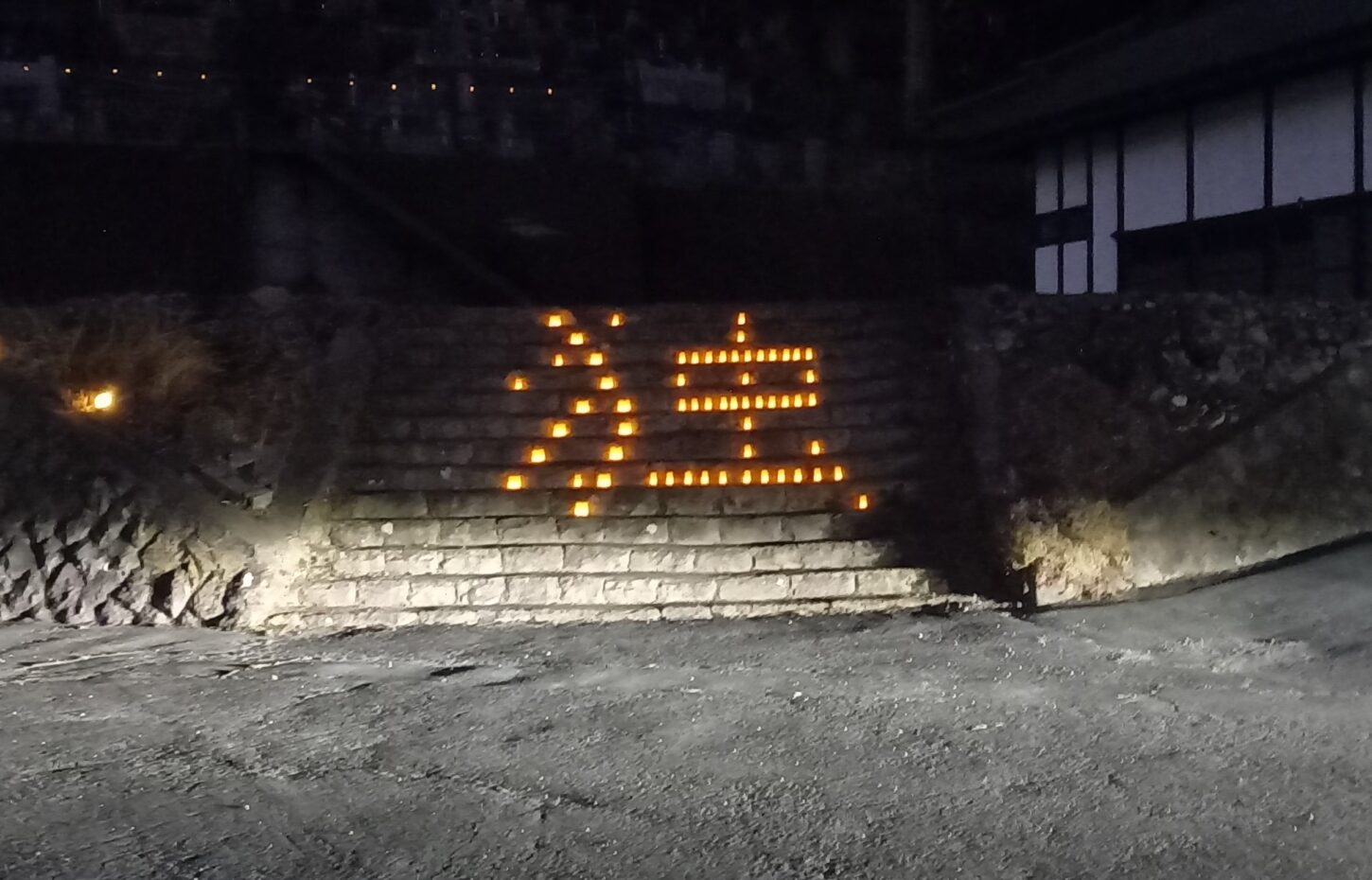

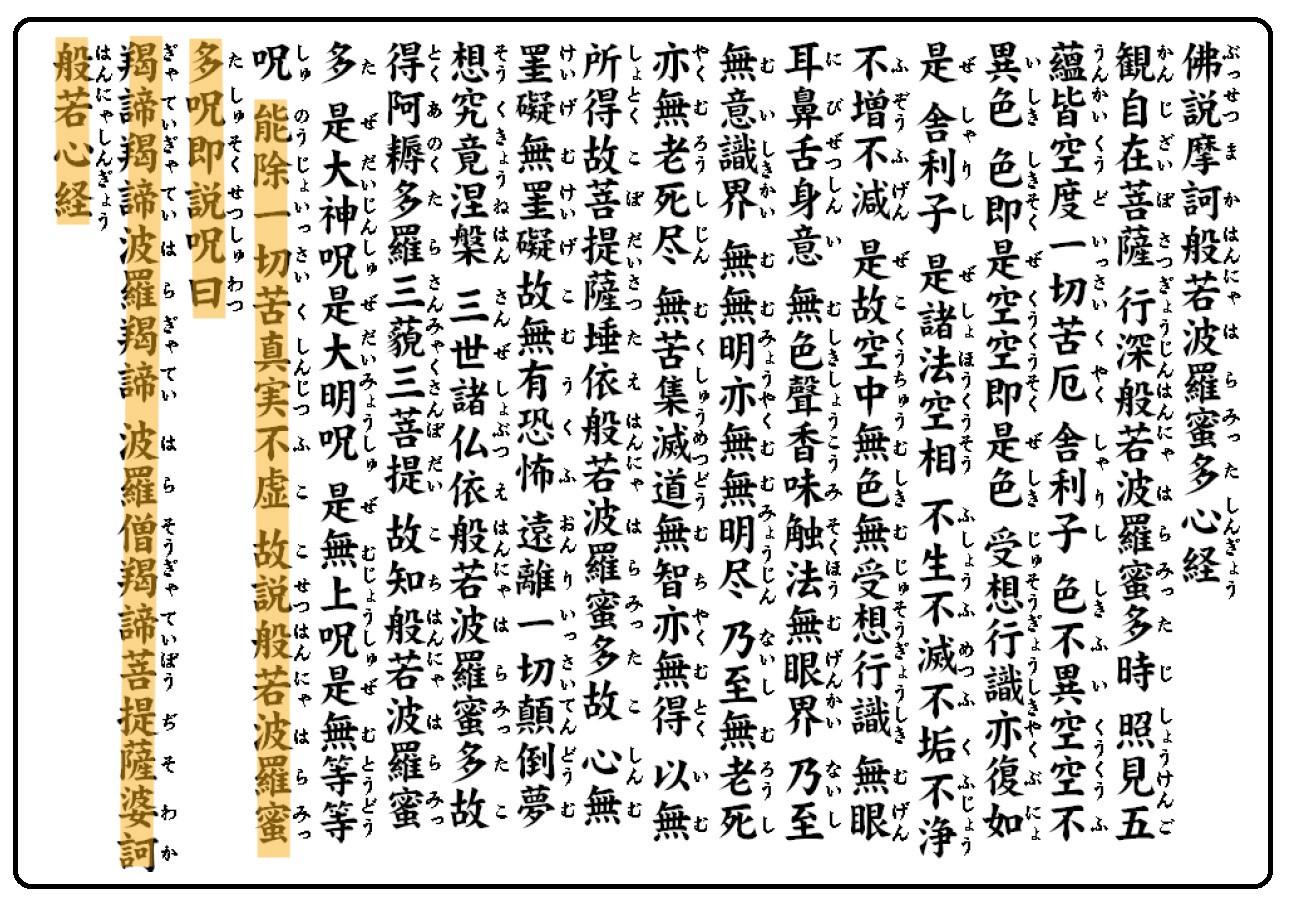

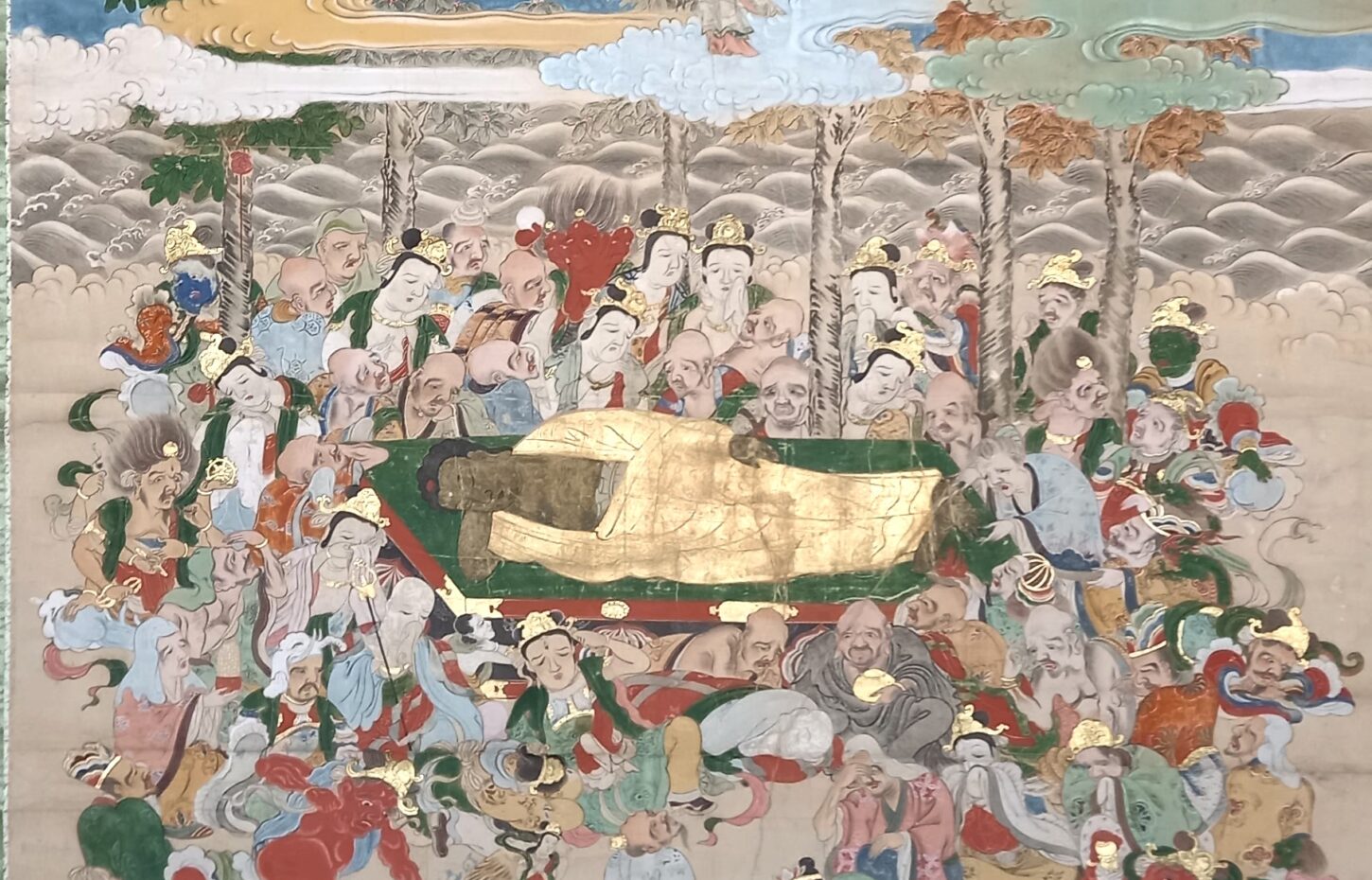
この記事へのコメントはありません。